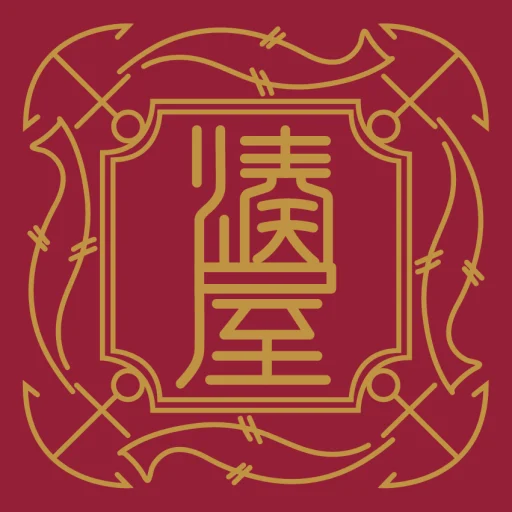天蚕の記憶
天蚕の繭を見たことがある。
茨城県北を流れる久慈川の中流域を訪れたときのことだ。川が切り開いた河岸段丘は、初夏の緑に沈んでいた。すずしく光る川面から視線を上げれば、県境まで続く山地が尾根をのばしている。この土地では、人間は川がつくったわずかな平地に、慎ましやかな街を営むばかりだ。そんな場所で、私ははじめて天蚕の繭を見た。
天蚕――正式な和名はヤママユ――は、さほど珍しい昆虫でもない。深山の奥に分け入らずとも、ちょっとした雑木林さえあれば、都市部でもお目にかかることができる。翅をひろげると十五センチメートルを超え、街灯に引き寄せられては虫嫌いの皆様に悲鳴を上げさせる、茶色くてでっかい蛾。それが天蚕の成虫だ。蝶よ花よと育てなければならない家蚕とは違って、野生で生き抜く逞しい昆虫である。
そのような事実に目をつむり、ことさら自然豊かな情景を描写したのは、若葉の森と久慈川のよどみ、天蚕の繭、あの日見た鮮烈な緑が、かわるがわる私の眼前にちらつくためだ。
そう、天蚕の繭は緑色なのだ。
絹糸をとるために飼育される家蚕、その近縁種である天蚕は、家蚕と同じ形でふたまわりほど大きな繭をつくる。葉の上に繭をつくるのだが、このとき近くの葉を糸で繋ぎ合わせて、繭のいちばん外側を覆ってしまう。天蚕の繭は周囲に溶け込むために、ほんの少し黄色がかった明るい緑色をしている。新緑の森の中では、この色が完璧な保護色として作用するわけだ。
私が出会った天蚕は、コナラの葉を二枚重ねた間に繭を作っていた。少し不器用な個体なのか、葉を使って外側を覆うのが下手で、繭の全形が見えてしまっていた。ゆえに、私が目をとめることができたのである。雑木林の外縁の、農道に面した木の枝、ちょうど人間の視線と同じくらいのところに、家蚕のそれよりも少し大きな繭がさがっていた。
恥ずかしながら私は、それを見たときに、すぐには天蚕の繭とわからなかった。家蚕ではない野蚕がいるという知識はもっていたものの、眼前にある色鮮やかな繭と結びつけられなかったのである。行動を共にしていた地元の知人に尋ねてようやく、繭の主を知った。三日三晩かけて絹糸を吐き、柔らかな砦の中で変態をはじめている一匹の芋虫が、その中に宿っているのだった。
絹を生み出す昆虫は数あれど、繭のかたちの完璧さでいえば、家蚕と天蚕が抜群だ。どちらの種の繭も、自然物とは思えないような整った楕円形を呈する。しかし不思議なのは、家蚕と天蚕は近縁とはいえ、直接の家畜化種と野生種の関係ではないということである。
家蚕の原種と目されている昆虫はクワコだ。中でも、中国大陸に生息するグループから分岐したと考えられている。色違いのような見た目をしている家蚕とクワコは、交雑さえ可能なほど遺伝的に近しい。その一方で、クワコの繭は非常に粗雑だ。かたちは不定形だし、厚みもさほどない。生糸の生産に最適化された繭をつくる現在の家蚕は、長い長い家畜化の果てに存在する。
ところが、自然選択の道のりを歩んできたはずの天蚕の繭は、生糸を取るために誂えたかのような構造をしている。野生回帰能力を完全に手放した家蚕とは全く異なる生存戦略の先に、きわめてよく似た形質に落ち着いた事実は、未だ謎多き進化の深遠さを思わせる。
人智の及ばぬところからもたらされる天蚕の繭を、人間はそれでも利用してきた。天蚕糸の生産は、現在では長野県安曇野市穂高有明などが有名であり、観光資源にもなっている。天蚕糸の特徴は、繭の色味を反映した独特の色合いと、家蚕の生糸よりも軽くて丈夫な性質にある。家蚕の生糸と交織にして製品化されていることが多い。希少な素材ゆえに高価になってしまうが、長年大切にしていく品と思えば法外でもない。尤も、懐事情の寂しさのために、私の箪笥には未だストールの一枚も迎えることはできていないのだが。
ところで残念なことに、天蚕糸の緑色は紫外線に弱く、経年によって黄色みが強くなってしまう。天蚕糸特有の機能性は失われることがないため、その価値を損なうものではないが、どうにかしてあの緑をとどめおく方法はないのか、と空想せずにはいられない。何しろ私の心は、あの夏の日から、鮮烈で輝かしい浅緑にすっかり奪われているのだ。
養蚕業が日本の主力産業を外れてから久しい今日、蚕とその近縁種に関する研究は低調である。天蚕糸の緑色を保持する研究は、熱心に進められているとは言い難い。野蚕を利用する生糸生産が行われているのはアジア地域に限られるため、関心を持つ研究者も限られるのが実情である。
優れた染色技術がある現代において、素材本来の色に執着するのはナンセンスなのかもしれない。しかし、新緑の森の中で天蚕の繭を見つけることがあれば、多くのひとが私と同じことを願うはずなのだ。
モバイル端末の方は横スクロール、PCの方はSHIFT+スクロールでお読みいただけます。
はしがき
第14回泉大津市オリアム随筆賞に応募したエッセイ。見事に落選。
応募してしまってから気づいたが、募集要項には「科学エッセイ求む」などとは全く書かれていなかったのである。誰が家蚕の野生化の過程など知りたいというのだ。
天蚕をはじめて見たときの喜びが、己の中であまりに特別な経験だったため、勢いのまま書いてしまった。反省しきりである。